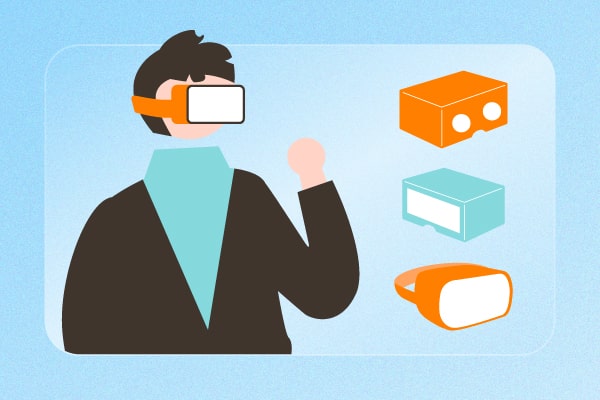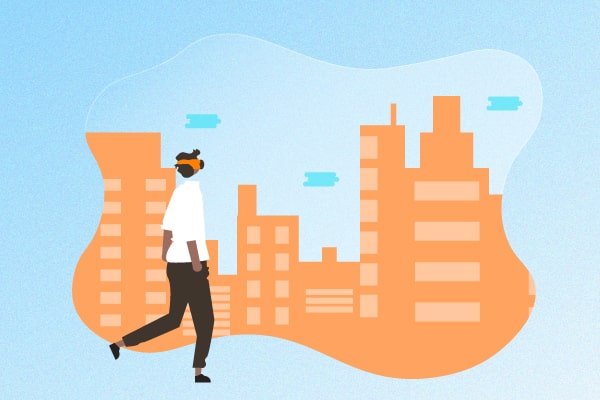- 2023/07/11
- 2025/04/23
【オンライン博物館】自宅でも楽しめるオンライン博物館とは?メリットや制作ツールを紹介
インターネット上で国内や海外の博物館を楽しめるオンライン博物館をご存じでしょうか?
自宅にいながらリアルな博物館と同じような臨場感を楽しめるほか、広報や集客面にも役立てられることから、マーケティング施策の一つとしても注目を集めています。
今回は、オンライン博物館を導入するメリットや、おすすめの制作ツールなどについて紹介します。
「オンライン博物館を導入して集客につなげたい」
「どんな制作ツールがあるのか知りたい」
上記のようにお考えの方は、制作ツールの詳細や導入事例も紹介しているので、ぜひご覧ください。
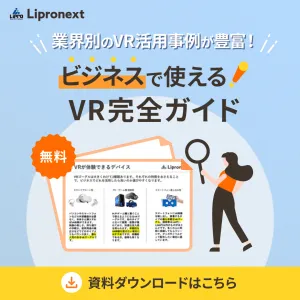
VRTipsは、 VRの最新情報やトレンドを発信する専門メディアです。ビジネスでの活用や事例に焦点を当てたお役立ち資料を用意していています。ぜひダウンロードください。
▶ 今すぐダウンロード(無料)
目次
1.オンライン博物館とは?

オンライン博物館とは、パソコンやスマートフォンなどのデバイスを使って、オンライン上で展示物を閲覧できるサービスです。
画像や動画で博物館内を見て回れるほか、VR機器を用いて臨場感あふれる体験が楽しめるなど、さまざまなコンテンツが用意されています。また、日本だけでなく、海外の博物館に展示されている作品も鑑賞できるため、遠方に住んでいる方でも24時間好きな時間にアクセスできます。
2.オンライン博物館を導入する5つのメリット
ここでは、オンライン博物館を導入すると得られるメリットを5つ紹介します。
- オフラインよりもコストを抑えられる
- 時間・場所の制約を受けずに閲覧が可能
- 遠方の方も作品が見られるため集客の幅が広げられる
- 来場者の正確なデータが集められる
- 展示物をオンライン上に保存できる
2-1.オフラインよりもコストを抑えられる
オンライン上で展示が可能なので、リアルな博物館の運営に必要な人件費や電気代といったコストを抑えられます。また、博物館にはパンフレットやチラシなどの印刷物が置かれていますが、オンライン博物館の告知にSNSなどを活用することで、印刷コストの削減にもつながります。
オンライン博物館の場合も導入コストは発生しますが、オフラインでの展示と比較すると安価で済む点が魅力です。
2-2.時間・場所の制約を受けずに閲覧が可能
オンライン博物館は営業時間を設ける必要がないため、24時間好きなタイミングで展示物を閲覧してもらえます。普段忙しくてなかなか博物館に行く時間が取れない人でも、オンライン博物館なら仕事や学校が終わった後でも楽しめます。
場所の制限がない点も、オンライン博物館の特徴です。博物館が遠くにあり気軽に足を運べない人でも、好きな場所で展示物を楽しめるので、潜在顧客への広報ツールの一つとして活用できるでしょう。
2-3.遠方の方も作品が見られるため集客の幅が広げられる
どこでも展示物を楽しめるオンライン博物館。遠方に住んでいる人も閲覧できることから、これまで博物館へ行く機会のなかった人にとっても身近なものになりました。
高齢の方や体の不自由な方も、オンライン博物館を利用すればいつでも閲覧できます。そのため、博物館側にとってはWeb上の集客の幅を広げられるチャンスとなります。
2-4.来場者の正確なデータが集められる
オンライン博物館を運営することで、利用者の年齢や性別、滞在時間など詳細なデータの収集ができるようになります。
滞在時間については博物館そのものや展示物ごとの滞在時間を分けてデータを集め、今後の展示方法を変更する場合などに活かせます。
オフラインでは来場者に紙のアンケートを募るなどアナログな手法がメインでした。しかし、オンライン博物館の活用でデジタル化に移行できるため、アンケートの収集も容易になります。
2-5.展示物をオンライン上に保存できる
リアルな博物館では展示物を保管する際に保管場所の確保が必要であるほか、展示物が劣化しないよう最適な環境を維持する必要があります。
オンライン博物館を活用することで、展示物をデータとして保存できます。展示物の老朽化によりオフラインでの展示が終了しても、オンライン上にアーカイブとして残しておくことができます。
これにより、人気のある作品の展示をやむなく終了することなく、半永久的に展示を続けられるようになるでしょう。
3.オンライン博物館の制作が可能なツール5選
オンライン博物館を導入する場合、制作が可能なツールは以下の5つがあります。表現したいイメージに合わせてツールを選ぶと良いでしょう。
- YouTube
- Google Arts&Culture
- HASARD
- Matterport
- 3DVista
3-1.YouTube
YouTubeでは博物館内の展示物を撮影し、動画コンテンツとして配信が可能です。展示物それぞれに解説を加えることで、来場できない人でも気軽にコンテンツを楽しめます。
動画配信ではリアルの博物館とは別に独自の企画を用意するなど、オフラインとは違った視点から博物館の魅力を発信できます。また、YouTubeではライブ配信もできるため、博物館内の様子をリアルタイムで配信し、博物館内の臨場感を伝えることも可能です。
▶︎▶︎YouTube 公式サイトはこちら
3-2.Google Arts&Culture
Google Arts&Cultureは、世界中の有名な博物館や美術館に展示されている作品を無料で閲覧できるGoogleのサービスです。閲覧できる芸術作品は20万件以上あり、そのほかに1,800件以上の博物館や美術館のストリートビューも楽しめます。
Google Arts&Culture上に展示したい場合、Googleへ招待リクエストを送る必要があります。リクエストを送り、展示が可能となった場合はGoogle側から招待メールが届き、サイト上への公開手続きに進みます。
Googleという巨大プラットフォームを活用できるため、遠方のユーザーへ向けた発信や博物館を身近に感じさせる施策を行いたい場合に有効なツールです。
▶︎▶︎Google Arts&Culture 公式サイトはこちら
3-3.HASARD
HASARDは、国内や海外の展示物が閲覧できるオンラインサービスです。美術館の制作がメインですが、博物館の制作も可能となっており、コストを抑えて展示を行いたい人にとっては最適なツールでしょう。
HASARDではオンライン個展の開催が可能。個展を開催するための費用は無料で、応募に必要な情報を送り、HASARD側での審査に合格すると個展の開催が可能です。
世界中の有名な作品の中に、自分が作り上げた作品を並べられる感動を味わえるツールです。
▶︎▶︎HASARD 公式サイトはこちら
3-4.Matterport
Matterportは、360°撮影可能なカメラを使用し、リアルな博物館と同じ空間をオンライン上に生成できるツールです。
真上から建物を閲覧できる「平面図」や、さまざまな角度から展示物を俯瞰できる「立体模型」など、通常の写真では見られない部分も詳細に表現できる機能が備えられています。
空間内に生成した展示物には動画や写真、リンクの挿入が可能なので、展示物の解説を取り入れたい場合などに活用できます。
高画質な映像を出力できる4Kを採用しているので、展示物の細かい部分まで興味を抱く人も、満足できる作品を提供できます。
下記の記事ではMatterportに関する詳しい内容を紹介してるので、ぜひご覧ください。
▶︎▶︎関連記事:ビジネスで使えるMatterportって?業界別事例とともに紹介
3-5.3DVista
3DVistaはスペインで開発された3Dバーチャルソフトです。3DVista内に含まれている「Virtual Tour Pro」を使うことで、オンライン博物館の作成が可能。また、展示物をクリックすることで、詳細な情報の閲覧もできます。
そのほかに、閲覧するWebサイトや3Dモデルの表示なども可能です。オンライン上に人物を埋め込み、博物館の案内人として登場させることもできるなど、幅広い活用ができる点も特徴です。
展示物についてより深掘りできる仕組み作りができるため、コンテンツの充実につながります。
4.オンライン博物館の導入事例3選
実際にオンライン博物館を導入し、運営している施設やサービスがあります。ここでは、以下の3つの事例を紹介します。
- 国立科学博物館
- 文化遺産オンライン
- 日本科学未来館
4-1.国立科学博物館

国立科学博物館では、オンライン博物館にMatterportを活用。ユーザーは外観や館内の展示物を自宅にいながら鑑賞できます。画面上の展示物に表示されているアイコンをクリックすると解説文が表示され、展示物の詳しい内容を読むことも可能です。
YouTubeチャンネルも開設しており、研究員によるオンラインギャラリーツアーと称して、博物館内の展示物を解説している動画も公開しています。
▶︎▶︎国立科学博物館 かはくVRはこちら
▶︎▶︎【国立科学博物館公式】かはくチャンネルはこちら
4-2.文化遺産オンライン

文化遺産オンラインは、文化庁が運営している日本国内の文化財や博物館に展示されている文化遺産をオンライン上で閲覧できるサイトです。建造物や絵画など、17のカテゴリからさまざまな作品が無料で楽しめます。
中には天然記念物や全国の史跡も閲覧できるので、日本の文化遺産について学びたいときに活用できるでしょう。
▶︎▶︎文化遺産オンライン 公式サイトはこちら
4-3.日本科学未来館

日本科学未来館は、GoogleArts&Culture内で人間とアンドロイドの違いや地球とのつながりなど、さまざまな展示作品が閲覧できます。
サイト内では、Googleストリートビューを使って施設内の各エリアを見て回ることもできます。普段は見ることができない、国際宇宙ステーション内部の探索も可能です。子どもだけでなく、大人の方も興味を抱くコンテンツが用意されているので、オンライン上で実際に施設にいるような体験を味わえます。
▶︎▶︎日本科学未来館 GoogleArts&Cultureはこちら
5.オンライン博物館を導入する際に注意すべき3つのこと
オンライン博物館の導入にはさまざまなメリットがありますが、以下の3点には注意が必要です。
- オンライン博物館の運営に必要な知識を習得する
- リアルの博物館で楽しめるコンテンツの充実も意識する
- 展示物の著作権に配慮する
5-1.オンライン博物館の運営に必要な知識を習得する
オンライン博物館の導入には、ツールを使いこなせるだけの知識が必要です。専門的な技術が必要な場合、技術の取得までに時間がかかるほか、トラブル時にすぐに対応できるだけのスキルがないと運営に影響を及ぼします。また、撮影の際には専用機材を使う場合もあるため、自分たちで作るのか制作会社に依頼するのかも事前に決めておきましょう。
5-2.リアルの博物館で楽しめるコンテンツの充実も意識する
オンライン博物館は気軽に利用できるだけに、リアルの博物館に対する価値が下がってしまうのではないかと思ってしまいます。
リアルの博物館は、オンラインでは味わえない臨場感あふれる展示や催しが可能な点が特徴です。それぞれの特徴を活かしながらコンテンツを容易し、双方の集客を伸ばしていく必要があります。
5-3.展示物の著作権に配慮する
オンライン上で展示する際、展示物の著作権に問題がないか事前に確認が必要です。リアルの博物館で展示されているからとオンライン博物館でもそのまま展示し、万が一著作権を侵害した場合、損害賠償請求に発展する恐れもあります。
著作権に触れる展示物に関しては、オンライン博物館では展示しないなどの対応も検討しましょう。
6.まとめ
オンライン博物館の活用で、いつでもどこでも博物館内の展示物を公開できるので、博物館側は広報・集客のツールとして活用できます。
今後5G/6Gと通信環境が進化し、Webコンテンツの表現方法が広がっていく中でさまざまな展示物を気軽に閲覧できるオンライン博物館の需要はさらに高まっていくでしょう。
好きなときに気軽にアクセスできるオンライン博物館を導入し、幅広い年代の方にアプローチをしましょう。
VRtipsを運営しているリプロネクストでは、オンライン博物館の制作について企画から開発までサポートしています。「こんなコンテンツは作れるだろうか」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。